一人暮らしでも、うつ病で障害年金は受け取れる?社会保険労務士が解説

「一人暮らしなら、障害年金は受け取れない」
どこかで、耳にしたことがあるかもしれません。
一般的な傷病であるなら、一人暮らしであることは
障害年金の受け取りに問題ありません。
ですが、精神疾患については、一人暮らしであることが
障害年金の受給に影響する場合があります。

監修:石井 智子
【保有資格】社会保険労務士 / 年金アドバイザー
【経歴】2018年8月 開業
「うつ病」「双極性障害」などの精神疾患で障害年金を受け取りたい方の手続き代行を「確実に・短い時間で・あなたの体力を減らさない」をモットーに行う。
目次
- ○ 一人暮らしなら、障害年金は受け取れない?
- ○ 一人暮らしであることが、精神疾患で障害年金申請の際になぜ問題になるのか?
- ・精神疾患の障害認定基準
- ○ 一人暮らしにかかわる診断書の記載注意点
- ○ 一人暮らしに関する生活のサポートを検討する
- ○ 一人暮らしの開始時期とその理由
- ○ 一人暮らしにかかわる診断書への記載箇所
- ○ 一人暮らしの状態は「病歴・就労状況等申立書」にも記載する
- ○ 一人暮らしを始めたら、障害年金は止まってしまうのか?
- ○ 一人暮らしの状況を更新の診断書に記載するとき
- ○ 一人暮らしのまとめ
- ○ LINEでのお問い合わせ
一人暮らしなら、障害年金は受け取れない?
一般的な傷病の人は、一人暮らしであっても障害年金に影響はありません。
障害年金を受け取ることができます。
ですが、統合失調症やうつ病、双極性障害といった
精神疾患にかかっている場合に限って、一人暮らしであることが障害年金に影響します。
時には一人暮らしが理由で障害年金を受け取れなくなったり、
本来2級であったとしても3級に認定されたりしてしまいます。
なぜでしょうか?
平成28年9月に策定された
「国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン」
に、一人暮らしにかかわる判断基準があるからです。
障害年金の審査が各地域ごとに審査されていたころ、精神疾患・知的障害についての審査に
地域差があったため、ガイドラインが策定されたという経緯があります。
このガイドラインが現在も基準となっています。
他の傷病にはこのようなガイドラインはありません。
そのため、精神疾患の場合のみ、一人暮らしの状態が審査に影響するのです。
「国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン」7ページを参照ください
一人暮らしであることが、精神疾患で障害年金申請の際になぜ問題になるのか?
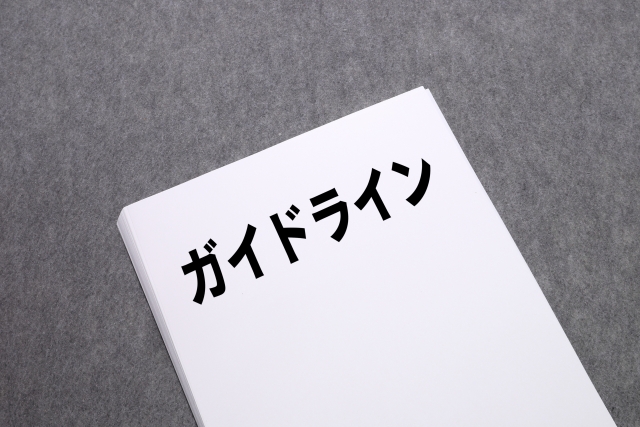
一人暮らしで生活が成り立っているなら、障害状態ではないと
判断されてしまうからです。
障害状態は、障害年金が支給される障害の状態に応じて、法令により、
障害の程度(障害等級1~3級)が定められています。
1級
他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできないほどの障害の状態です。
身のまわりのことはかろうじてできるものの、それ以上の活動はできない方(または行うことを制限されている方)、
入院や在宅介護を必要とし、活動の範囲がベッドの周辺に限られるような方が、1級に相当します。
2級
必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、
労働によって収入を得ることができないほどの障害です。
例えば、家庭内で軽食をつくるなどの軽い活動はできても、それ以上重い活動はできない方(または行うことを制限されている方)、
入院や在宅で、活動の範囲が病院内・家庭内に限られるような方が2級に相当します。
3級
労働が著しい制限を受ける、または、労働に著しい制限を加えることを必要とするような状態です。
日常生活にはほとんど支障はないが、労働については制限がある方が3級に相当します。
2級でいう「家庭内で軽食をつくるなどの軽い活動」しかできないような場合、
一人暮らしは不可能なはず、という判断なのです。
「国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン」によると
考慮するべき要素として
①現在の病状又は状態像
②療養状況
③生活環境
④就労状況
⑤その他
以上の5項目が挙げられています。
その中で、
③生活環境
「考慮すべき要素」には、
「家族等の日常生活上の援助や福祉サービスの有無を考慮する」
こととされています。
「具体的な内容例」としては、
独居であっても、日常的に家族等の援助や福祉サービスを
受けることによって生活できている場合は、それらの支援の状況
を踏まえて、2級の可能性を検討する。
「独居であっても(以下略)」という記載は、
いいかえれば、一人暮らしであっても、何らかの援助を受けていれば2級の可能性がある。
援助がなければ、3級である。
そのように読みかえることができます。
精神疾患に関してだけ存在しているガイドラインに明記されていることから
一人暮らしであるかどうかは、重要な判断基準の一つなのです。
精神疾患の障害認定基準

精神疾患については、障害認定の基準はどのように書かれてているでしょうか?
「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準(令和4年4月1日改正,、最新のものです)」
には、14の項目に分けて障害認定基準がまとめられています。
障害認定基準
第1節 眼の障害
第2節 聴覚の障害
第3節 鼻腔機能の障害
第4節 平衡機能の障害
第5節 そしゃく・嚥下機能の障害
第6節 音声又は言語機能の障害
第7節 肢体の障害
第8節 精神の障害
第9節 神経系統の障害
第10節 呼吸器疾患による障害
第11節 心疾患による障害
第12節 腎疾患による障害
第13節 肝疾患による障害
第14節血液・造血器疾患による障害
いずれの障害であっても、検査や計測の結果と共に日常生活への影響の程度が
基準となって障害等級が決められています。一人暮らしについて
書かれていることはありません。
「第8節 精神の障害」の中では、
精神の障害の程度は、その原因、諸症状、治療及びその病状の経過、
具体的な日常生活状況等により、総合的に認定する (略)
認定に当たっては具体的な日常生活状況等の生活上の困難を判断するとともに、
その原因及び経過を考慮する。
このように、「具体的な日常生活状況等の困難」の程度も判断の
基準となっています。
国民年金・厚生年金保険 障害認定基準 精神の障害 56ページをご覧ください
一人暮らしにかかわる診断書の記載注意点
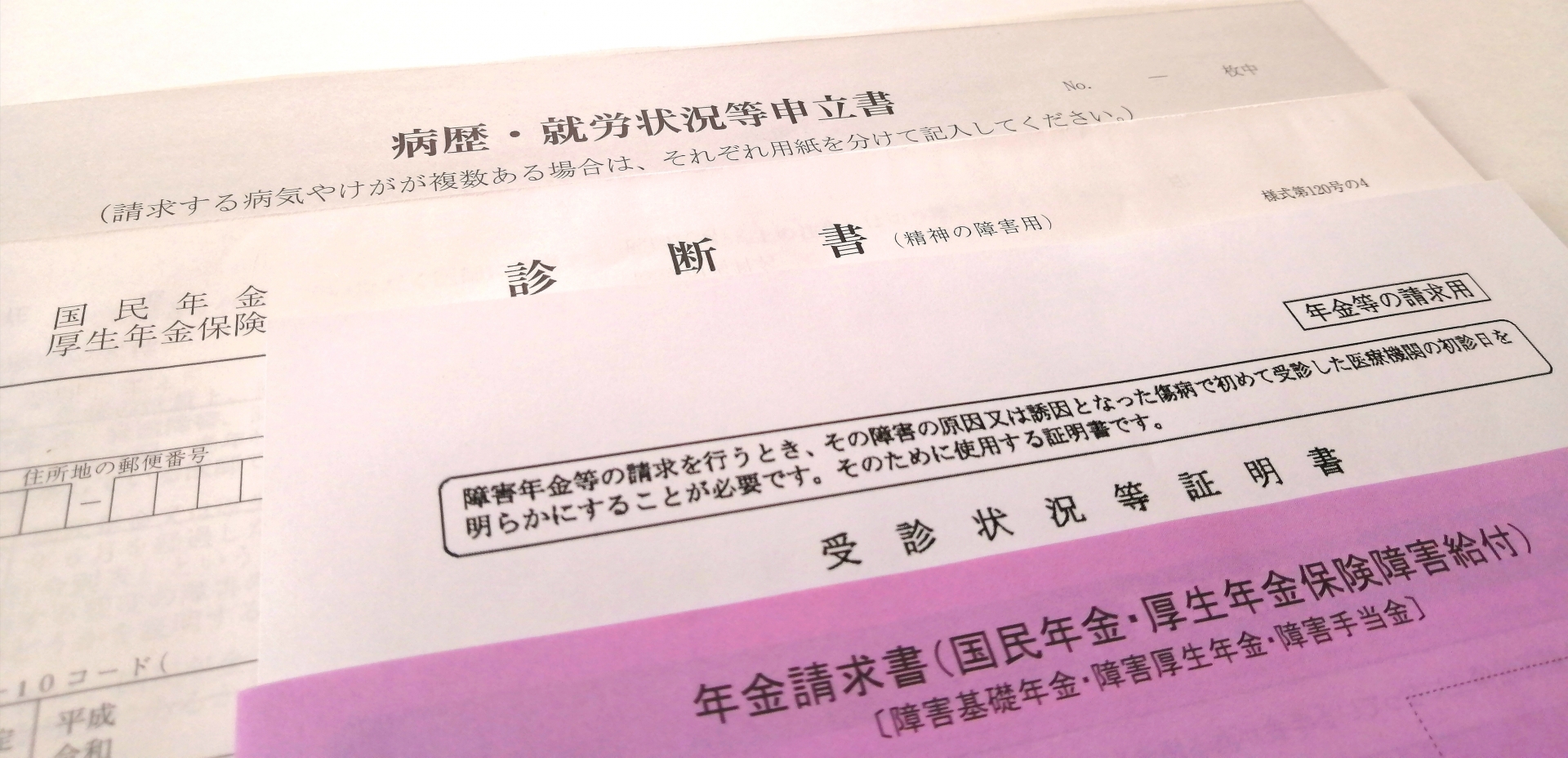
障害年金の申請のための診断書は8種類あります。
1 眼の障害
2 聴覚・鼻腔機能・平衡感覚・そしゃく・嚥下機能・音声又は言語機能の障害
3 肢体の障害
4 精神の障害
5 呼吸器疾患の障害
6 循環器疾患の障害
7 腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害
8 血液・造血器・その他の障害
ここの8種類の中で、日常生活の状況について説明し、
段階付けをする欄があるのは、8 精神の障害 の診断書だけです。
この日常生活の状況について、一人暮らしであることを記載します。
様々な事情から、重症の精神疾患でありながら一人暮らしをせざるを得ない場合には、
主治の医師とよく相談することが必要です。
この欄に
・一人暮らしの事実を記載
・一人暮らしをせざるを得ない状況
・受けているサポートの内容と頻度 等
を医師に記載してもらいます。
記載してもらうために医師との相談が必要なのです。
一人暮らしに関する生活のサポートを検討する

重症の精神疾患の場合、だるさや疲労感があり、
体が思うように動かせないケースが大変多いです。
そのため働くことはもちろんのこと、
自身を健康に保つための、清潔保持や食事、運動などができなくなります。
本来なら誰かのサポートを受けて、日常のこまごまとしたことを
頼る必要があるにもかかわらず、一人暮らしをせざるを得ない人ももちろんいらっしゃいます。
身の回りの整理整頓や、ゴミ出しといった清潔保持ができないまま、月に1回の診察日に
やっとのことで出かけていく、といった状態は
「一人で生活できている」とは言えない状態です。
それなのに、一人暮らしという事実だけで、書類審査で結果が出てしまう
障害年金申請は、注意が必要です。
まず、一人暮らしの事実を変えられませんから、
受けられるサポートを検討してください。
・担当の医師と相談し、訪問看護を受ける
・役所の福祉課で受けられるサポートはないか
上記のような公的なサポートは費用もかかります。
受けることができないならば、友人や親せきをたよって
週のうち数回定期的にそうじや買い物をお願いしてみてください。
お住いの地域のボランティア活動で、生活のサポートを
してくださるケースもあります。
どんなに苦しくてもひとりで何とかしようとなさっては
障害年金が遠のく可能性があります。
病状が重くても一人暮らしなら3級の可能性があるわけです。
初診日に会社勤めをしていて、障害厚生年金を申請できるなら
1,2,3級までありますので、まだ何とか障害年金の可能性がありますが、
初診日に国民年金のため障害基礎年金の申請ならば、
1,2級までしかありません。
一人暮らしの開始時期とその理由
一人暮らしを始めることになった時期も基準に影響する場合があります。
もともと元気でいる間に一人暮らしをしていた場合は、
残念ながら審査の影響へはほとんどありません。
例えば、家族からの過干渉によりメンタル不調になり、
一人暮らしをせざるを得なかった場合。
あるいはDVによりメンタル不調で、住まいを移し一人暮らしを始めた場合。
このようなメンタル不調の要因から離れるための一人暮らし
であるときには、審査の際に考慮されます。
医師の指示であればなお審査の基準となります。
いつ一人暮らしを始めたか?
その時期はメンタル不調と関連しているか?
これがポイントとなります。
一人暮らしにかかわる診断書への記載箇所
8種類の診断書のうち、日常生活にかかわる記載箇所があるのは
精神の障害の診断書だけです。
具体的に診断書のどの箇所にどのような記載があるといいでしょうか?
まず、精神の障害用の診断書は隅々まで読んでおきましょう。
一人暮らしに関して記載できるのは3か所あります。
【1 診断書の表 】
⑦ 発病から現在までの病歴及び治療の経過、内容、就学・就労状況等、期間、その他参考となる事項
この欄は、発病から現在までの主だった事柄を記載する欄です。
文末に、以下のような記載ができます。
例 「現在独居で、週に3回程度の家事代行を受けている」
【2 診断書の裏 】
表の⑩障害の状態
ア 現在の病状又は状態像 イ 左記の状態について、その程度・症状・処方薬等を具体的に記載してください。
引き続き 裏
ウ 日常生活状況
1家庭及び社会生活についての具体的な状況
(ア)現在の生活環境 在宅 を選びます。
同居者の有無は、無 を選びます。
以下の欄が一番重要です。
(イ)全体的状況
例 独居のため人との交流はほとんどない。週3回近隣に住む姉の家事支援
を受けており、この支援がなければ生活が成り立たない。
【3 診断書の裏 】
⑪ 現症時の日常生活活動能力及び労働能力
この欄は生活が成り立っているか、働くことができるかを簡潔に記載する欄です。
文末に書き加えることが可能です。
例 独居であるが、地域の介護支援を受けており、支援が無ければ生活が成り立たない。
2に、記載があれば1と3はどちらかに書かれていれば良いという程度です。
一人暮らしの状態は「病歴・就労状況等申立書」にも記載する

障害年金申請時には、診断書のほかに
「病歴・就労状況等申立書」を提出します。
自身で記載することができる書類です。
最初の申請時には診断書を補う形で自分の状況を申し立てることができます。
この書面に一人暮らしでサポートを受けている頻度や内容を伝えることができます。
買い物、掃除、公的支払いの手続き、通院の介助、などサポート内容はさまざまあると思います。
診断書と異なり、記載スペースも広いので、充分書けるはずです。
一人暮らしを始めた時期も記載忘れがないように。
一人暮らしを始めたら、障害年金は止まってしまうのか?

障害年金申請の際に一人暮らしではありませんでした。
その後一人暮らしを始めざるを得なくなったとしたら、
すぐに障害年金は一人暮らしを理由にストップするでしょうか?
そのようなことはありません。
どこかで一人暮らしが発覚して、年金機構に連絡が届くのでは?との心配は必要ありません。
生活状況を確認するのは、次回の診断書の提出時に確認します。
診断書提出までは、一人暮らしを始めたからという理由で障害年金は止まりません。
更新の診断書に一人暮らしであってもサポートを受けていることが
記載されているなら、障害年金は継続受給できる可能性があります。
次回の診断書提出月は、年金証書一番下の左側に記載されています。
精神疾患は永久認定ではありません。必ず更新があります。
更新の際には、指定の期日前に日本年金機構より郵送されます。
一人暮らしの状況を更新の診断書に記載するとき
障害年金申請の際には、「診断書」の他に「病歴・就労状況等申立書」を併せて
提出できますから、一人暮らしについての状況説明は、診断書を補うことが可能です。
ですが、更新の時は診断書のみの提出です。
サポートなしでは一人暮らしが成り立たないことを
診断書に記載することが必要です。
診断書のどの部分に何を記載すると良いでしょうか?
更新の際に提出する診断書は、書類の名称を
「障害状態確認届」といいます。
内容は最初に申請した時の診断書とほとんど変わりません。
異なっているところは、
障害状態確認届(診断書)の表に
④ 最近1年間の治療の経過等を書く欄があります。
最初の申請の際には発症から現在までについての記載でしたが、
最近1年間と期間が短くなっています。
エ の通院歴についても
申請時は全期間でしたが、ここ5年間の通院歴に短縮しています。
裏面は同じです。
更新の際も申請時と同様に独居であるが、サポートを受けている
ことを申請時の診断書同じ箇所に記載します。
最後の「備考」欄での記載も可能です。
一人暮らしのまとめ
いかがだったでしょうか。
一人暮らしだから、障害年金をあきらめなければならない、と不安になる必要はありません。
主治医ともよく相談し、サポートなしで生活が成り立たないことを、診断書に明記できれば、
障害年金受給の可能性は高くなります。
障害年金受給中の場合にも
一人暮らしを開始したからといってすぐに年金の受給がストップしてしまうことはありません。
また、一番多いご心配が
「一人暮らしを始めたら、どこからか一人暮らしの事実が年金機構に伝わって
すぐに年金がストップしてしまう」
というものです。
確認のタイミングは、更新の「障害状態確認届(診断書)」提出の時です。
住民基本台帳とつきあわせて、更新時に確認するため、
更新までは受給できます。すぐにストップすることはないのでご安心ください。
LINEでのお問い合わせ

ご質問はLINEでのお問い合わせが一番早くお返事できます。
社会保険労務士が直接お答えいたします。
どうぞご遠慮なく!お問い合わせください。
平日 8:00~20:00
土曜日 8:00~14:00
日曜日のみお休みです。

